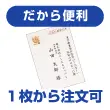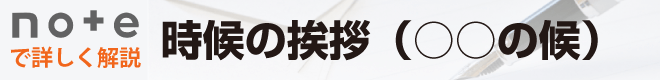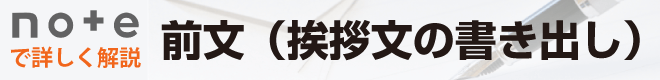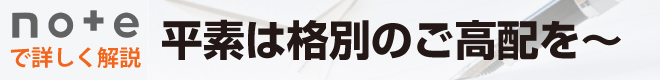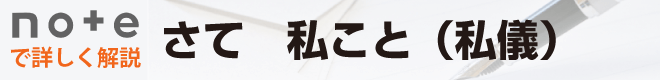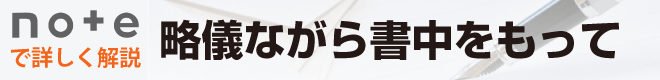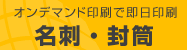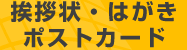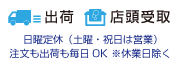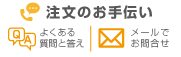挨拶状・案内状・お礼状の時候の挨拶・頭語結語 前文(書き出し)見本や句読点などマナー解説
挨拶状を書くときに必要な知識やルール・マナーを解説いたします
挨拶状の用語・知識・マナーなど 書き方とルールまとめ
お電話で注文完了までお手伝い。電話を繋ぎながら一緒に画面操作してナビゲート可能。電話:03-5911-4811(9:00〜19:00)
時候の挨拶(○○の候)・季節の言葉(季語)
時候の挨拶、季節の言葉の通年対応したテンプレート集、選ぶだけで使えます。
”時下”ますます〜という表現
「時下」から始まる挨拶もあります。時候の挨拶はどれを選べばよいか悩むことが多いでしょう。
そのようなときに万能に使えるのが「時下」です。差出が月をまたぎそうな場合も「時下」は便利です。
「拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」というように使います。
各月ごとの時候の挨拶・季節の言葉(季語)
時候の挨拶(季語)はその月のものを使った方が丁寧な印象になります。月別にまとめてありますのでご参照ください。(ビジネスでは伝統的な表現、○○の候が適しています)
※例文にある「○○の候」のままでも適した時候の挨拶をプリントメイトが選んで印刷します
1月(睦月:むつき)の時候の挨拶
♦初春の候(1/7頃まで) ♦新春の候(1/7頃まで) ♦仲冬の候(小寒1/5まで) ♦小寒の候(1/6〜1/19頃) ♦厳寒の候(1月中旬・下旬) ♦酷寒の候(1月中旬・下旬) ♦厳冬の候(1月中旬・下旬) ♦寒風の候(1月中旬・下旬) ♦大寒の候(1/20〜)
●寒気厳しき折柄 ●松の内の賑わいも過ぎ
●年が明け まだ来ぬ春が待ち遠しく感じられます
●松もとれましたが あいかわらず寒い日が続いています
●寒さもいっそう身にしみる昨今ですが
●寒中とはいえ ここ数日はあたたかい日が続いておりますが
●初春とはいえ厳しい寒さが続いております
2月(如月:きさらぎ)の時候の挨拶
♦晩冬の候(2/4頃まで) ♦節分の候(2/5頃まで) ♦残寒の候(2月上旬・中旬) ♦立春の候(2/4〜2/17頃) ♦余寒の候(2/4〜2月末) ♦春寒の候(2/4〜2月末) ♦残雪の候(2/4〜2月末) ♦梅花の候(2/4〜2月末) ♦雨水の候(2/18〜2月末)
●余寒厳しき折柄 ●三寒四温の時節
●立春とは名ばかりでまだまだ寒い日が続いております
●春の陽気が待ち遠しい今日この頃
●まだまだ余寒きびしい日が続きますが
●日差しにも春の訪れを感じるようになりましたが
●梅のつぼみも膨らみ 日中はいくらか寒さもゆるんで参りました
3月(弥生:やよい)の時候の挨拶
♦弥生の候(3月全般) ♦浅春の候(3月上旬) ♦軽暖の候(3月上旬・中旬) ♦早春の候(3月上旬・中旬) ♦啓蟄の候(3/5〜3/19頃) ♦春暖の候(3月中旬・下旬) ♦萌芽の候(3月中旬・下旬) ♦春風の候(3月中旬・下旬) ♦春分の候(3月下旬) ♦仲春の候(3月下旬)
●春寒次第に緩み ●春草萌えいづる季節を迎え
●桃の節句を過ぎ ようやく春めいて参りました
●春の風が快い季節となりましたが
●日ごとに春の訪れを感じるようになりましたが
●うららかな日差しがまぶしい今日この頃ですが
●旅立ちの春を迎え 日増しにあたたかさを感じています
4月(卯月:うづき)の時候の挨拶
♦陽春の候(4月全般) ♦桜花の候(4月上旬) ♦花冷えの候(4月上旬) ♦清明の候(4/4〜4/19頃) ♦春爛漫の候(4月上旬・中旬) ♦春粧の候(4月上旬・中旬) ♦春和の候(4月上旬・中旬) ♦春日の候(4月中旬・下旬) ♦惜春の候(4月中旬・下旬) ♦清和の候(4月中旬・下旬) ♦穀雨の候(4/20〜4月末)
●若葉萌えいづる頃 ●春たけなわ
●桜の花のたよりが聞かれる頃になりました
●春もたけなわの頃となりました
●うららかな春の日和となりました
●若草が萌えたち春も深まってまいりました
●春の嵐に桜吹雪も舞っております
5月(皐月:さつき)の時候の挨拶
♦新緑の候(5月全般) ♦晩春の候(5月初旬) ♦暮春の候(5月初旬) ♦立夏の候(5/5〜数日程度) ♦万葉の候(5月上旬) ♦葉桜の候(5月上旬) ♦薫風の候(5/5〜5月末) ♦青葉の候(5月中旬・下旬) ♦深緑の候(5月中旬・下旬) ♦万緑の候(5月中旬・下旬) ♦軽暑の候(5月中旬・下旬) ♦軽夏の候(5月中旬・下旬)
●晩春の一時 ●緑照り映える時節
●新緑の香りがすがすがしい季節になりました
●風薫るさわやかな季節となりました
●すがすがしい初夏の風に吹かれ 心もはずむ季節となりましたが
●青く澄み渡った空がすがすがしく感じる季節
●五月の空が気持ちよく晴れわたっています
6月(水無月:みなづき)の時候の挨拶
♦麦秋の候(6/5頃まで) ♦首夏の候(6月初旬) ♦薄暑の候(6月上旬) ♦芒種の候(6/5〜6/20頃) ♦入梅の候(6月中旬) ♦紫陽花の候(6月中旬) ♦梅雨の候(6月中旬・下旬) ♦長雨の候(6月中旬・下旬) ♦梅雨寒の候(6月中旬・下旬) ♦夏至の候(6/21以降) ♦向暑の候(6月下旬) ♦小夏の候(6月下旬)
●清々しい初夏を迎え ●初夏の風に肌も汗ばむ頃
●あじさいの色が美しく映えるころとなりました
●長雨が続いておりますが
●毎日の雨に気もふさぐ気分になりがちな毎日ですが
●木々の緑もますますその青さを増しておりますが
●長かった梅雨もあけ 初夏の風が爽やかな季節となりました
7月(文月:ふみづき)の時候の挨拶
♦仲夏の候(7/6頃まで) ♦七夕の候(7月上旬) ♦梅雨明けの候(7月上旬〜梅雨次第) ♦小暑の候(7/7〜7/21頃) ♦盛夏の候(7月中旬・下旬) ♦夏祭の候(7月中旬・下旬) ♦大暑の候(7/22頃〜) ♦猛暑の候(7月下旬) ♦炎暑の候(7月下旬) ♦酷暑の候(7月下旬) ♦烈暑の候(7月下旬) ♦極暑の候(7月下旬)
●暑気厳しき折柄 ●蝉の声に暑さを覚える今日此頃
●降りしきる蝉の声に夏の盛りを感じる頃になりました
●暑さ厳しき折 その後お変わりございませんか
●今年の夏は一段と厳しいですが
●梅雨も明け 本格的な夏を迎えましたが
●海山が恋しい季節になりました
8月(葉月:はづき)の時候の挨拶
♦大暑の候(8/6頃まで) ♦立秋の候(8/7〜8/22頃) ♦晩夏の候(8月上旬・中旬) ♦季夏の候(8月上旬・中旬) ♦暮夏の候(8月上旬・中旬) ♦避暑の候(8月中旬) ♦残暑の候(8/7〜8月末) ♦秋暑の候(8/7〜8月末) ♦納涼の候(8/7〜8月末) ♦初秋の候(8/7〜8月末) ♦処暑の候(8/23頃〜) ♦向秋の候(8月下旬)
●残暑厳しき折 ●朝夕涼味を覚える頃
●立秋とは名ばかりの厳しい暑さが続いています
●朝夕にはかすかに秋の気配を感じます
●残暑がひときわ身に染む毎日ですが
●夏も終わりに近づき 虫の声が聞かれるころとなりましたが
●秋まだ遠く 厳しい残暑が続いています
9月(長月:ながつき)の時候の挨拶
♦新秋の候(9/6頃まで) ♦初秋の候(9/6頃まで) ♦重陽の候(9/9頃) ♦野分の候(9月上旬・中旬) ♦白露の候(9/7〜9/21頃) ♦涼風の候(9月中旬) ♦秋晴の候(9月中旬・下旬) ♦爽秋の候(9月中旬・下旬) ♦秋色の候(9月中旬・下旬) ♦仲秋の候(9月中旬・下旬) ♦秋分の候(9/22頃〜) ♦秋桜の候(9月下旬) ♦秋雨の候(9月下旬) ♦初露の候(9月下旬)
●爽やかな季節を迎え ●二百十日もことなく過ぎ
●朝の空気に爽秋の気配が感じられる頃となりました
●今年は格別に残暑が厳しいようですが
●一雨降るごとに涼しさも増してきました
●残暑もようやく和らぎましたが
●コスモスが風に揺れ 朝夕はしのぎやすくなって参りました
10月(神無月:かんなづき)の時候の挨拶
♦秋麗の候(10月全般) ♦夜長の候(10月全般) ♦爽涼の候(10月初旬) ♦秋晴の候(10月上旬) ♦秋冷の候(10月上旬) ♦仲秋の候(10月上旬) ♦寒露の候(10/8〜10/22頃) ♦紅葉の候(10月中旬・下旬) ♦錦秋の候(10月中旬・下旬) ♦霜降の候(10/23頃〜) ♦菊花の候(10月下旬) ♦季秋の候(10月下旬) ♦朝寒の候(10月下旬)
●菊花薫る時節 ●天高く馬肥ゆる秋
●菊薫る好季節となりました
●秋もいよいよ深まりを見せてまいりました
●木の葉も日一日と色づいてまいりました
●さわやかな秋晴れの続く今日此頃
●芸術の秋となりました
11月(霜月:しもつき)の時候の挨拶
♦霜降の候(11/6頃まで) ♦深秋の候(11/6頃まで) ♦暮秋の候(11/6頃まで) ♦立冬の候(11/7〜11/21頃) ♦落葉の候(11月上旬・中旬) ♦深冷の候(11月上旬・中旬) ♦霜秋の候(11月上旬・中旬) ♦初霜の候(11月中旬・下旬) ♦晩秋の候(11月中旬・下旬) ♦向寒の候(11月中旬・下旬) ♦霜寒の候(11月下旬) ♦氷雨の候(11月下旬) ♦小春日和の候(11月中・天気次第) ♦冷雨の候(11月中・天気を見て)
●落ち葉散りしく時節 ●鮮やかな紅葉の頃
●吐く息の白さに 秋の終わりを感じる頃となりました
●暮れ行く秋を寂しく感じる今日この頃
●朝夕冷え込む季節になりましたが
●落ち葉が風に舞う季節となりました
●街路樹もすっかり葉を落とし ゆく秋の気配に寂しさを感じる季節となりました
12月(師走:しわす)の時候の挨拶
♦寒冷の候(12月全般) ♦初冬の候(12月上旬) ♦大雪の候(12/7〜12/20頃) ♦師走の候(12月上旬・中旬) ♦寒気の候(12月上旬・中旬) ♦初雪の候(12月上旬・中旬) ♦寒気の候(12月中旬) ♦冬至の候(12/21頃〜) ♦年末の候(12月中旬・下旬) ♦歳末の候(12月下旬) ♦歳晩の候(12月下旬)
●歳末ご多端の折 ●寒気厳しき折柄
●師走に入り何かと多忙な日々が続いております
●木枯らしの吹く季節となってまいりました
●日ごとに寒さが募ってまいります
●ポインセチアが美しい紅色を見せるころ
●年の瀬の寒さが身にしみる季節となりました
頭語と結語の組み合わせ(拝啓・敬具など)
頭語と結語の組み合わせ例、テンプレート集、選ぶだけで使えます。
季節の挨拶状に頭語・結語は不要
年賀状・暑中見舞い・残暑見舞い・寒中見舞いなどの季節の挨拶状は「謹賀新年」「暑中も見舞い申し上げます」などの冒頭あいさつが既に「頭語」の役目を果たしていますので必要ありません。
また、死亡通知状、抗議文、お詫び状などにも必要ありません。
お見舞い状・お悔やみ状には頭語が不要
お見舞い状などは頭語・前文を省略します。それにより「突発的事実を知って、とるものもとりあえず書いた」という姿勢を示すようにします。
お見舞い状に頭語を入れるとすれば「急啓」「前略」「冠省」などで、頭語を省略していきなり主文に入る場合でも結語には必ず「草々」と入れます。
お悔やみ状は頭語を省いて結語に「合掌」で良いと思います。
挨拶状の内容による頭語と結語
挨拶状に使う「拝啓と敬具」「謹啓と謹白」等の頭語・結語にはおおよその組み合わせルールがあります。
一般的な挨拶状
頭語●拝啓 ●拝呈 ●啓上 ●一筆申し上げます(女性用)
結語●敬具 ●敬白 ●拝具 ●かしこ(女性用)
よく使う組み合わせ●拝啓ー敬具
あらたまった挨拶状
頭語●謹啓 ●恭啓 ●粛啓 ●謹呈 ●謹んで申し上げます
結語●謹白 ●謹言 ●敬白 ●かしこ(女性用)
よく使う組み合わせ●謹啓ー謹白 ●謹啓ー謹言
急用の場合
頭語●急啓 ●急呈 ●急白 ●取り急ぎ申し上げます
結語●草々 ●敬具 ●不一 ●かしこ(女性用)
よく使う組み合わせ●急啓ー草々
返信の場合
頭語●拝復 ●謹復 ●復啓 ●お手紙拝見いたしました
結語●敬具 ●拝具 ●建白 ●拝答 ●かしこ(女性用)
よく使う組み合わせ●拝復ー敬具
再送の場合
頭語●再啓 ●追啓 ●再呈 ●重ねて申し上げます
結語●敬具 ●敬白 ●拝具 ●かしこ(女性用)
よく使う組み合わせ●再啓ー敬具
前文を省略する場合
頭語●前略 ●冠省 ●略啓 ●前略ごめんください(女性用)
結語●草々 ●不一 ●不尽 ●かしこ(女性用)
よく使う組み合わせ●前略ー草々
前文(挨拶文の書き出し)について
ますますご清栄のことと〜等、挨拶文の書き出しパターン(すぐに使えます)
前文:挨拶文の書き出し(書き始め)とは
前文とは「拝啓※頭語」+「○○の候※時候の挨拶」+「ますますご清栄のことと〜」のブロック全体を差しますが
ここでは「ますますご清栄のことと〜」の部分についてまとめました
前文の意味と使い分け
前文にも意味があるので、会社・法人宛ての場合と個人宛ての場合で使い分けます。
法人・団体向け(代表取締役や法人の担当者へ送る際もこちら)
ご盛栄・ご繁栄・ご隆盛・ご隆昌などに書き替えできますが、これらは会社が栄えている様子を表しますので個人には使えません
個人向け(取引先の個人宛てでも友好としならこちら)
それ以外にご清栄も使えます(健康と繁栄の両方を指すため、法人でも個人でも使用してもよい)
様々な前文の例
●お元気にされていますか
●その後お変わりございませんか
●ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
●いよいよご清祥のこととお喜び申し上げます
●皆様に於かれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます
●皆様にはますますお元気でお過ごしと存じます
●皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じ上げます
平素は格別のご高配を賜り〜の有無
挨拶状での前文に次ぐ決まり文句、平素は格別のご高配を〜の有無について
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
挨拶状での儀礼的な表現で「いつも大変お世話になっております」という意味です。
「ご高配」は「ご厚情」「お引き立て」「ご愛顧」などに書き替えできますが、常套句として「ご高配」を使うことが多いです。
ビジネス挨拶状には入れておきたい一文です
ビジネス挨拶状は「会社」と「会社」の挨拶ですので、日頃のお付き合いに感謝を述べてから本題に入るのがマナーだと思います。
※不特定多数へ配布するビジネス文書での告知にも、お決まりのご挨拶として使われています。
※「ご高配」は畏まった表現ですので社内や個人的な関係には適しません。場違いであるとともに、よそよそしいイメージになってしまいます。
サービスや製品のご利用にお礼を述べてから始めたい場合
一般的な使い方
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
日頃より弊社をご愛顧いただきありがとうございます
具体的に使う場合
日頃より弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます
日頃より弊社○○○○(サービス名)をご利用いただき誠にありがとうございます
お店なら
いつも当店をご愛顧いただき誠にありがとうございます
私こと・私儀(わたくしぎ)
自分自身のことについて書くときに使う、挨拶状での一般的な表現
挨拶状では一般的な表現(ぜひ使ってください)
「この度 弊社では〜」のように「私こと」が登場しない例文もあります。
「私こと」とは遜り(へりくだり・相手への謙遜)表現で、自分のことについてご挨拶する際に用いる表現です。
「私こと」「私儀」は同じ意味ですが「私こと」の方がやや柔らかい印象を与えます。
挨拶状では「私個人の事で恐縮ですが…」という謙遜の気持ちから、行末に下げるのが習わしになっています。※慣れないかもしれませんが挨拶状では一般的な表現です。
「私こと」「私儀」は他に比べてやや(控えめに)小さく書くのが礼儀とされていますので、プリントメイトの挨拶状でもやや小さく印字しております。
仏事挨拶状の「○○ 儀」について
これも「私儀」と同じように相手への丁寧な表現(謙譲表現)です。
葬儀の看板などで使われる「○○ 儀 葬儀式場」の「儀」と同じです。
日常で使う機会のない表現ですので無理に使う必要はありませんが、付けた方が相手に対しては丁寧な表現となりますのでお勧めです。※ちなみに、この場合は行末には下げません。
誤用に注意
「さて 私こと 山田太郎は〜」という使い方はしません。
→ 「さて 私こと(改行)」「(改行後は)本文を書きます」
スピーチ等の自己紹介で耳にする [通称]こと[本名]とは別物ですので注意して下さい。
句読点・段落を使わないのは何故
挨拶状に句読点や段落落しが使われないのには、いくつかの理由があります。
入れない理由には諸説ありますが、おおまかに以下の通りです。
失礼にあたるという見方
古くは漢文に使われる「レ点」などの名残で、漢文を読むのに「レ点」などの記号を必要とする人は学のない人・乏しい人など見なされていた為に、相手に対して失礼にあたるという見方があります。
また、句読点は明治時代に入るまで使われておらず、最初は学校で子どもが読みやすいようにと使われ始めたものでした。
もともと無かったものですので、文章にわざわざ句読点を付けるのは相手を子ども扱いしているということで使われてきませんでした。
縁起を担ぐ意味
文章を区切る句読点を使わないことで、今後の流れやご縁を区切らないという縁起を担ぐ意味もあります。
句読点や段落を使わずに書くコツ
読点の代わりにはスペース、句点の位置では改行するのが基本です。
段落を使わなくても「前文」「主文」「末文」と「記書き」を意識すれば、まとまりのある読みやすい挨拶文にすることができます。
A4ビジネス文書での句読点
A4挨拶状でビジネス文書として書かれたものには、句読点や段落が使われているものがあります。
差出月(差出日)と吉日について
挨拶状の最後にある日付をいつにするのかを解説します。
挨拶状を書いた日(月)を入れる
相手に届く月日では無いので注意して下さい。
ただし、「書いた日」と「届く日」が月を跨いだりする場合は、数日間のことですので分かり易さを優先して届く月日を記載することもあります。
※注文時点では挨拶状を出す日が決められないために、月末の注文では翌月の差出月を記載しておくのも1つの方法です。
差出月まで(日にちは省略)するのが一般的
特にビジネスでの挨拶状などは、書いた日に特別な意味が無い場合は差出月までとします。
ただし、葬儀や法要などのお礼状のように「その当日にすぐに書きました」という意味を込めたり、お詫び状のように「書いた日を明記」したほうがよいケースでは省略しないようにしましょう。
「吉日」とするケース
一般的な挨拶状なら「差出月まで」でも「吉日」を付けても意味は同じです。
ただし、吉日には「良い日を選んで書いた」という意味が込められるため、適さない挨拶状がありますので注意が必要です。
良い日取りなどない「弔事・仏事」などはもちろん適しませんし、お詫び状やお礼状などは「直ちに出すのがマナー」ですので、日取りを選んで書くという「吉日」は適さないということです。
略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます
結びの挨拶である「略儀ながら書中をもって〜」について解説します。
礼儀を示す決まり文句
「お会いしてお伝えするべきところ、今回は挨拶状でのお知らせとさせていただきます」という意味で使われます。
挨拶状に於いては決まり文句となっており、エチケットとして入れる一文となります。
招待状のように、もともと書状で案内するような場合には不要です(入れても問題ありません)
いくつかのバリエーション
まずは略儀ながら〜、甚だ略儀ながら〜、略儀ながら取り急ぎ〜など、追加の意味をもたせることもできます。
更に丁寧にする
本来であれば拝趨のうえご挨拶申し上げるべきところ〜などを付け加えて、更に丁寧に気持ちを表現することもできます。
記書き(別記)について
記書き(別記)を活用して、本文と要点の両方を分かりやすく書く方法について
要点は記書き(別記)にまとめる
挨拶状を書いていると要件の詳細も挨拶文中に織り込みがちですが、それに加えて感謝や抱負まで伝えたいとなると、分り難く長い文章になってしまいます。
そのようなケースでは、要点を記書きに別記すると分かりやすくできます。
基本的には二つ折り挨拶状の「右面」に挨拶文、「左面」に記書きするというのが一般的です。
左記のとおり、左記により
「別記」で要件を述べる場合、主文の中でそのことに触れなければなりません。
これを「記の伏記」といいますが「左記のとおり」「左記により」として、詳細は記書きをご覧くださいと表現します。
別記する内容は、文章で説明するのではなく箇条書きにするとよいでしょう。
読みやすくなる以上の効果
別記を活用することにより、読みやすくなる以上の効果も期待できます。
「詳細が明確に書かれ間違いが無くなる」とともに「挨拶文での感謝や抱負が伝わりやすい」というものです。
記書きに「以上」は必要?
「別記」したら「以上」で締めくくるのが、ビジネス文書として周知のルールですが、挨拶状に於いてはこの限りではないのが実際です。
挨拶文の書き方マナー(簡単チェック)
挨拶状で気を付けたいポイントの最終チェックなどでお使いください
挨拶状を書く上で知っておくべきポイント(まとめ)
このページの詳しい説明とは別に簡単なチェック項目をまとめました
 添削サービスとは?
添削サービスとは?
挨拶文が上手く繋がらない時の修正依頼やマナー・習慣などのチェックにご利用いただけます。
例文の必要箇所を書き替えた場合は、殆ど手直しが必要無い挨拶文ですので「例文入力チェック」をご利用いただけます。例文の内容を書き替えた場合は「例文書き替え添削」、自作または大幅に書き方場合は「自作挨拶文添削」をご利用(注文画面で依頼)いただけます。
時候の挨拶は
ビジネスでの挨拶状は「伝統的な表現(○○の候)」を用いるのが一般的です。
※「時下ますます〜」というオールマイティーな言い方もあります。
※「○○の候」としておけば適した時候の挨拶をプリントメイトが選んで印刷します
≫【月別】時候の挨拶一覧
拝啓・敬具
頭語と結語にはよく使われる組み合わせがあります。
※「拝啓」「敬具」か一般的。少しかしこまりたい場合は「謹啓」「謹白」がお勧め
≫【頭語・結語】の組み合わせ
ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
ビジネスでも個人でも「ご清栄」としておけば問題ありません。
※「ご清祥」「ご健勝」は個人向けの表現になります
≫【前文】の選び方
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
ビジネス挨拶状では、ぜひ入れたい一文です。
※「会社」と「会社」の日頃のお付き合いへの感謝(同僚や友好関係には使いません)
≫【ご高配】以外のパターン
私こと・私儀(わたくしぎ)
※「この度 弊社では〜」のように「私こと」が使われない例文もあります。
「私こと」とは自分のことについてご挨拶する際の丁寧な表現です。
行末に下げるのがマナー。※挨拶状では一般的な表現
※誤用に注意※ さて 私こと 山田太郎は〜という使い方はしません。
≫【私こと】の詳しい説明
句読点・段落
挨拶状には入れないのがフォーマル(A4挨拶状でのビジネス文書を除く)
※文章のまとまりを意識するなどのコツがあります
≫【句読点・段落】の説明とコツ
差出月(日)と吉日
日付は省略して書いた月までが一般的(月末近くなら翌月にしてもOK)
※葬儀・法要のお礼状・お詫び状など日付までがよいものもある
※吉日を使うことができる(適さないものもある)
≫【吉日】の使い方など
略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます
挨拶状でご挨拶にて失礼させていただきます という意味。
※案内状など例外はあるが、ビジネスでのエチケットとして入れておきたい
※言い方にはいくつかのバリエーションがある
≫【略儀ながら書中〜】の使い方
記書き(別記)
要点は別記すると読みやすく間違いがない
2つ折りの挨拶状の左右に「挨拶文」と「記書き」分ける
≫読みやすい【別記】の方法
その他マナー(追伸・続柄・忌み言葉)と知識
その他のポイントと難しい漢字の読み方などの知識をご紹介
仏事挨拶状の解説は別ページがあります
法事・法要の挨拶状や会葬礼状、死亡通知といった仏事挨拶状の専用解説ページです。
仏事・弔事・法事・法要等の一連の挨拶状・案内状・お礼状を整理して解説しています。
追伸について
追伸について
「副文」「なお書き」「追って書き」ともいい、その事柄を主文に書くと冗長で解り難くなる場合に、その部分を意識的に取り出して目立たせ注意を引く為に使います。
主文に書き漏らしたことを書き加えるのではなく、念を押したいことや注意事項があるときに利用します。
●なお・・・については・・・ ●追って・・・については・・・
弔事関係(死亡通知や喪中はがき)や謝罪などには使わない方がスマートです。
主文以外の内容をついでに付け加えるような構成になってしまいますので印象が良くないかもしれません。
挨拶状で使われる読みにくい漢字と意味
挨拶状の中で使われる独特な漢字の読み方と意味、使い方を紹介します。
| 拘らず | [かかわらず] ○○であるのに。 |
|---|---|
| 御事 | [おんこと] ご様子 |
| ご鄭重 | [ごていちょう] 心がこもって礼儀正しい |
| ご厚志 | [ごこうし] 深い思いやり※弔事では香典 |
| ご厚誼 | [ごこうぎ] 情愛がこもった親しい付き合い |
| ご弔慰 | [ごちょうい] 死者を弔い遺族を慰める |
| ご厚情 | [ごこうじょう] 思いやりのある心。心遣い。 |
| ご芳情 | [ごほうじょう] ご厚情の敬語 |
| ご懇情 | [ごこんじょう] 真心のこもった心遣い |
| ご懇篤 | [ごこんとく] 心がこもっているさま |
| ご来駕 | [ごらいが] 式、催しへ出席の敬語 |
| 供花 | [きょうか][ぐげ] 故人に供える花 |
| 供物 | [くもつ] 神仏に供える物 |
| 粗餐 | [そさん] 料理のへりくだった言い方 |
| 粗箋 | [そせん] 手紙のへりくだった言い方 |
| 封緘 | [ふうかん] 手紙などの封を閉じること |
| 態々 | [わざわざ] 労力を惜しまずに |
|---|---|
| 偏に | [ひとえに] ただただ。もっぱら。 |
| 茲に | [ここに] この時。この場で。 |
| 拝趨 | [はいすう] こちらから出向くこと |
| 拝眉 | [はいび] 会うことのへりくだった言い方 |
| 乍ら | [ながら] ○○ではございますが |
| 愈々 | [いよいよ] ますます。より一層 |
| 旁々 | [かたがた] ○○を兼ねて・○○がてら |
| 衷心 | [ちゅうしん] まごころの奥底 |
| 過日 | [かじつ] 先日 |
| 忌明け | [きあけ] 四十九日を迎えること |
| 偲び草 | [しのびぐさ] 志(神道やキリスト教) |
| 以って | [もって] 手段・方法にて |
| 〜の由 | [〜のよし] 〜と承っておりますが |
| 仕ります | [つかまつります] 行うの謙譲語 |
| (誰々)儀 | [こと] (誰々)に関しての |
続柄(つづきがら)
挨拶状では続柄で身内を表現します。続柄の例・一覧、選ぶだけで使えます。
続柄(つづきがら)一覧(身内の呼び方)
≪夫から見た続柄≫
| 親等数 | 続柄 | 表記例 |
|---|---|---|
| 0親等 | 妻 | 妻、家内 |
| 1親等 | 子 | 息子、娘、長男、次男、長女、次女 |
| 父 | 父、実父、養父 | |
| 母 | 母、実母、養母 | |
| 妻の父 | 父、義父、岳父 | |
| 妻の母 | 母、義母、丈母 | |
| 2親等 | 孫 | 孫、孫息子、孫娘 |
| 兄弟姉妹 | 兄、弟、姉、妹 | |
| 妻の兄弟姉妹 | 兄、弟、姉、妹、義兄、義弟、義姉、義妹 | |
| 祖父母 | 祖父、祖母 | |
| 妻の祖父母 | 祖父、祖母、義祖父、義祖母 |
| わかりにくそうな続柄 | 表記例 |
|---|---|
| 配偶者の祖父、祖母 | 義祖父、義祖母 |
| 配偶者の祖祖父、祖祖母 | 義祖祖父、義祖祖母 |
| 両親の兄・両親の姉の夫 | 伯父 |
| 両親の姉・両親の兄の妻 | 伯母 |
| 両親の弟・両親尾妹の夫 | 叔父 |
| 両親の妹・両親の弟の妻 | 叔母 |
これ意外にも例えば妻の父であれば、分かりやすいように「妻の父○○」とか「(妻の名前)の父○○」などのように書いても問題ありません。(ちなみに上の表は、妻から見た続柄として見ても、ほとんど同じです。)
ただ、妻から見た続柄の場合は、「岳母」と「丈母」が使えませんので注意。「岳父」「丈母」は、夫から見た妻の父母に対してだけ使える尊称です。
各続柄の敬称(相手方の呼び方)
相手方の親族の呼び方です
| 父 | ご尊父様・お父上様・お父様・父君 |
|---|---|
| 母 | ご母堂様・お母上様・お母様・母君 |
| 祖父 | ご祖父様・おじい様・祖父君 |
| 祖母 | ご祖母様・おばあ様・祖母君 |
| 夫 | ご主人様・旦那様 |
|---|---|
| 妻 | ご令室様・奥様・奥方様 |
| 息子 | ご令息様・ご子息様 |
| 娘 | ご令嬢様・お嬢様 |
忌み言葉・重ね言葉(避けるべき表現)
挨拶状では内容により、相応しくない言葉、避けるべき表現があります。一覧にしてあります。
忌み言葉・重ね言葉等の避けるべき表現
挨拶状には避けたほうが良いとされている「忌み言葉」「重ね言葉」というものがあります。
縁起が悪い、良くないことを連想させる言葉を使わない気遣いからで、挨拶状の用途によって異なります。
開店・開業・新築などに関する忌み言葉
つぶれる、負ける、だめになるなどに関連した言葉は避けます。また、火事に関連して、火に関する言葉もタブーです。
●つぶれる ●倒れる ●崩れる ●壊れる ●閉じる ●朽ちる ●落ちる ●失う ●さびれる ●衰える ●行き詰まる ●負ける ●敗れる ●破れる ●傾く ●揺れる ●焼ける ●燃える ●焼く ●火 ●煙 ●赤い(=赤字につながる)
結婚に関する忌み言葉
わかれる、こわれる、だめになる、破れる、去る、終わるなどの意味合いの言葉は避けます。また、重ね重ねなどの「もう一度」を連想させる言葉もタブーです。
●別れる ●分かれる ●離れる ●別々になる ●切れる ●割れる ●飽きる ●壊れる ●嫌い ●捨てる ●破れる ●終わる ●倒れる ●降りる ●去る ●消える ●解ける ●流れる ●枯れる ●冷える ●冷める ●忙しい ●戻る ●負ける ●再三 ●二度 ●二回 ●痛い ●病む ●帰る ●返る ●滅びる ●断つ ●だめになる ●繰り返す ●短い ●苦しい ●寂しい ●悲しい ●薄い ●重ね重ね ●重々 ●度々 ●返す返す ●再び ●再度 ●またまた ●皆々様 ●近々 ●くれぐれも ●いろいろ ●しばしば ●次々 ●なおまた ●わざわざ ●再三再四 ●たまたま ●いよいよ ●再々
また言い換えで回避「ご多忙中」→「ご多用中」、「お返事」→「ご連絡」
ひらがなにする「是非」→「ぜひ」 省略する「またまた」→「また」等で回避する手もあります
出産に関する忌み言葉
失う、死ぬなどを連想させる言葉は避けます。
●失う ●消える ●落ちる ●流れる ●衰える ●死ぬ ●苦しむ ●破れる ●くずれる ●四(=死)
長寿に関する忌み言葉
死ぬ、終わる、枯れるなどの言葉は避けます。
●終わる ●枯れる ●衰える ●倒れる ●寝る ●死ぬ ●病む ●寝つく ●折れる ●途切れる ●朽ちる ●やめる ●ぼける ●四(=死) ●九(=苦)
葬儀に関する忌み言葉
たびたび、などの重ね言葉は避けます。生死に関する直接的な言葉もタブーです。
●重なる ●重ね重ね ●再度 ●再々 ●再三 ●くれぐれも ●また ●たびたび ●しばしば ●ときどき ●返す返す ●皆々様 ●続く ●長引く ●死 ●苦 ●死亡 ●死去 ●生存 ●四(=死) ●九(=苦) ●浮かばれない ●迷う
病気・けが見舞いの忌み言葉
長引く、悪いなどに関連した言葉は避けます。
●死 ●苦しむ ●四(=死) ●九(=苦) ●寝る ●寝つく ●悪い ●長い ●長引 ●繰り返す ●再び ●またまた ●再々 ●滅びる ●枯れる ●衰える ●力尽きる ●落ちる ●折れる
天災・災害見舞いの忌み言葉
再び、ばらばらになるなどを連想させる言葉は避けます。
●再び ●再々 ●再度 ●重ね重ね ●返す返す ●重なる ●続く 長引く ●長い ●離れ離れ ●離れる ●ばらばらになる ●苦しい ●失う 見失う